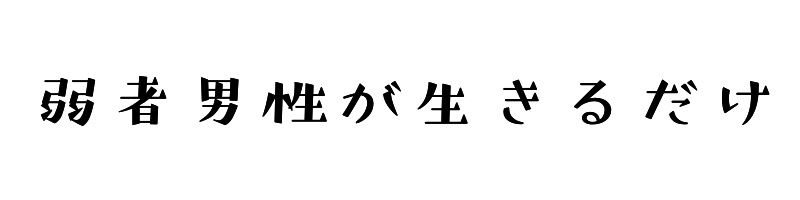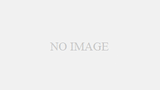楽観的な自殺とは「自分で寿命を決める」ようなものである。
長く生きることを望んでいない人間にとっては、病気や事故などで偶然「死が訪れるのを待つ」よりは、自らの意思とタイミングと方法で「人生の幕を降ろすのできる自殺は悪くない選択肢」だ。
「人生に絶望したから」とか「生きているのが辛いから」など、消極的な自殺はあまり良いものとは思えない。
しかし、
- 「長く生きていても退屈だから」
- 「これ以上は労働をしたくないから」
- 「特にやりたいことや目的が無いから」
など、どちらかというと「楽観的というか効率的な理由」で行う自殺は、命を捨てるというよりも「自分の寿命を決める」ようなものである。
誰もかれもが長く生きることを望んでいるわけではない。
にも関わらず、死ぬことの自由性を「道徳的・倫理的な面で制限している」のはおかしな話に思う。
制限する理由や目的も理解できる。
だが、人間社会で生きるという「割と難度が高く面倒極まりないこと」を、長く生きることを望んでいない人間に強いるような「価値観の押し付けや圧力」は、改めて見直すべきではないだろうか。
一般的に人間の死は「病気や事故、事件に巻き込まれる」など、外的要因が発生するまで待たなければならない。
しかし、私はこれがあまり納得できていない。
外的要因が発生するか否かはほとんどギャンブルであり、下手をすれば「長生きしたくない人間が長生きしてしまう」という事態が起きてしまう。
長く生きるということはその分だけ、労働や納税などの義務を行わなければならなくなるし、生活における様々なトラブルにも対応せねばならなくなっていく。
このような
が幸せだとは私には思えない。
ある日 突然に死が訪れるのを待つよりも、自分で寿命を決めて「死を迎える」という考え方がもっと広まってもいいと思う。
生きることについては「ある程度の自由性が認められている」のに、こと、死に関しては途端に「選択肢が狭められていて不自由極まりない」のは息苦しくて仕方がない。